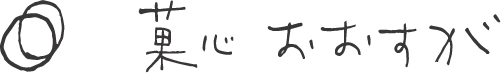水無月
水無月
6月といえば水無月。
もっちりした外郎と小豆の組み合せは、涼感もあります。
水無月の始まりは、室町時代の京都。
小豆は悪魔払い、三角形は暑気払いの氷、または龍神の鱗を形作っているそうです。
6月30日は、半年間の穢れを祓い、残りの半年の無病息災を祈る「夏越祓(なごしのはらえ)」の日。
この時期は、神社に茅の輪が設置され、参拝者はここをくぐって厄除けをします。
当時の宮中では、夏越祓として
氷室から取り寄せた氷を口にしていましたが、
庶民の間では、水は貴重であったため、
氷になぞらえたお菓子を作り、夏の無事を祈ったそうです。